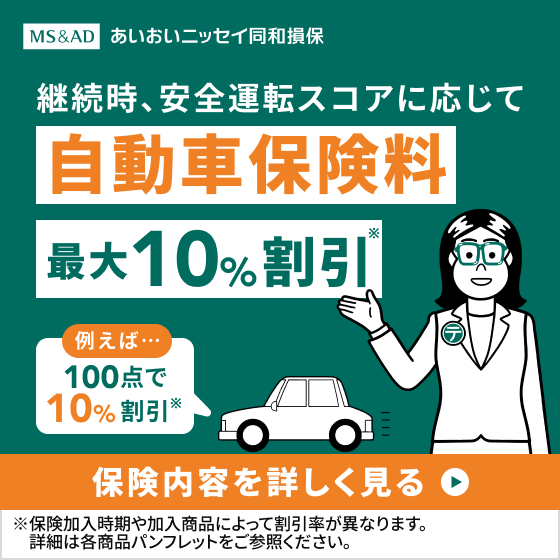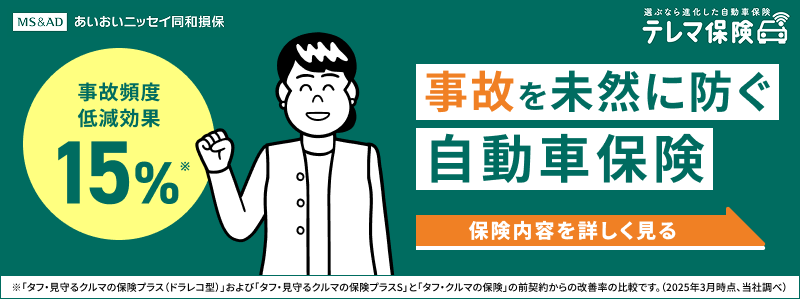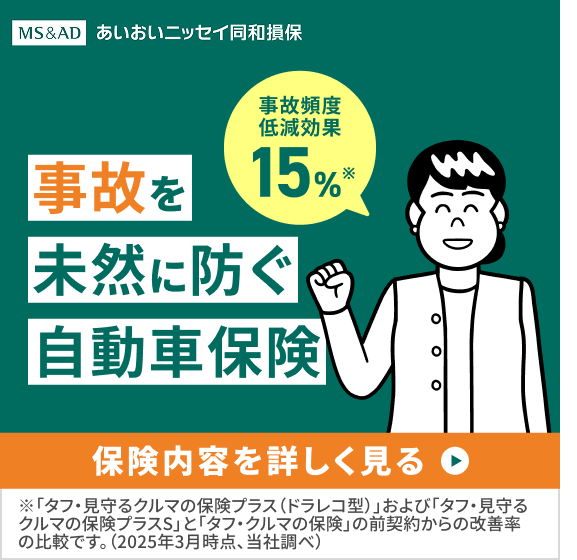テレマティクス技術による安全運転の見える化
今回のイベントで使用されたテレマティクス技術は、「テレコミュニケーション(通信)」と「インフォマティクス(情報工学)」を組み合わせた造語から生まれた先進技術です。参加者の車両に手のひらに収まるサイズの GPS機能付き車載器を設置し、スマートフォンアプリとBluetooth接続することで、以下の5つの走行データをリアルタイムで取得・分析します。

● 急加速の頻度と強度
● 急ブレーキの回数と程度
● 急ハンドルの発生状況
● 速度超過の状況
● スマートフォン使用検知
これらのデータはスマートフォンアプリに即時反映され、100点満点で採点。さらには、走行ルート、所要時間、各項目の評価が星の数で表示されます。イベント期間中の累計スコアも可視化され、参加者は自身の運転傾向を客観的に把握し、継続的な改善に取り組むことができます。安全運転を意識したエコドライブの実践により、CO2排出削減量も数値化され、環境保護への貢献度も実感できる仕組みとなっています。このシステムは、あいおいニッセイ同和損保が提供する「テレマティクス自動車保険」で使用されている技術を応用したもので、事故後のための保険から事故を起こさない保険への転換を体現した、次世代型の取り組みです。
大激戦の結果発表!上位10チームに表彰状を授与
会場にはスコア上位10チームの代表が出席し、表彰式が行われました。100点満点中、上位陣はわずかコンマ数ポイントの僅差という、非常にレベルの高い競争となりました。
上位のチーム名と平均スコアは次のとおりです。
総合ランキング
| 順位 | チーム名 | チーム平均スコア |
|---|---|---|
| 1位 | 国東市スマートドライバー | 99.445点 |
| 2位 | 大分市生安男女 | 99.376点 |
| 3位 | (株)小野自動車軽スパ高城店 | 99.342点 |
| 4位 | 大分県交通安全協会 さる~る | 99.286点 |
| 5位 | 大分トヨタ自動車(株) 総務1 | 99.272点 |
| 6位 | チーム竹尾 | 99.253点 |
| 7位 | 日本自動車連盟大分支部 JAF大分 | 98.918点 |
| 8位 | 日本生命玖珠営業部 池田チーム | 98.843点 |
| 9位 | 大分トヨペット(株)「いそがばまわれ」 | 98.459点 |
| 10位 | 株式会社優紀 | 98.302点 |
今回、大分県内で取り組むのは初めてだったため、「SAFE TOWN DRIVE OITA」の取組みに賛同頂いた皆様を中心に参加していただきました。 上位入賞者の顔ぶれを見ると、日頃から安全運転に対する意識の高い方たちがより一層、注意しながら日々のドライブに取り組んでいたことがうかがえます。
入賞チームの声
第1位:国東市スマートドライバー
優勝を果たした「国東市スマートドライバー」は、公共交通を担当する国東市職員3人組のチームです。チーム代表の吉岡さんは「まずは優勝という結果にびっくりしています!」と一言。受賞の喜びとともに、貴重な気づきを話してくれました。

「市役所職員として、常日頃から公共交通の事業者さんに安全運転を呼び掛ける立場なので、私たちが率先垂範しなければならないと考えていました。実際に取り組んでみると、意外と標識の見落としなどが多いなど気づきもあり、反省も多かったというのが本音です」
吉岡さん自身、運転歴25年以上のベテランドライバーですが、今回のイベントを通じて、「免許を取得した頃の初心を思い出し、緊張感のある運転ができました」と振り返ります。「大分県の事故ゼロは、私たち一般ドライバーの日々の注意が作っていくと考えています。このような安全運転の意識や今回の学びを広めたい」と、決意を示しました。
第3位: (株)小野自動車軽スパ高城店
株式会社小野自動車は、自動車販売・整備工場として任意保険販売も手掛ける、まさに自動車のプロフェッショナルです。「車や交通安全に携わる立場として、こうした催しがあると聞き、すぐに参加を決めました」と参加の経緯を語ってくれました。

株式会社小野自動車 取締役会長 小野 康夫 氏
「自分では安全運転しているつもりでも、スコアとしてスピードが出ている、急ブレーキだと示されると、言い訳できません。今回のイベント参加で、自らの運転のクセを見直すきっかけになり、新鮮な経験でした」と、可視化されることのメリットをあげてくれました。さらに「ゆとりを持って運転することの大切さを実感しました。朝の国道10号線は、先を急ぐ車が多く走っています。しかし、10~20分余裕をもって家を出れば、のんびり運転でも出勤はちゃんと間に合う。これは発見でした」と自身の運転習慣を振り返ります。
CO2削減で地球環境に貢献できることや、ゆとり運転の大切さを自身が実感したことで「ふだん自動車保険を取り扱う中で接するお客さんにも、安全運転の重要性を伝えていきたいです」と意欲的に語ってくれました。
収集されたデータは55万km!「交通安全マップ」の寄贈
表彰式に続き、今回のイベントで収集された貴重な走行データを活用した「交通安全マップ」の寄贈式も行われました。あいおいニッセイ同和損害保険の萩原智明執行役員より大分県警察本部交通部長・後藤和樹氏へ目録が贈呈され、官民連携による交通安全対策の新たな一歩が記されました。
この交通安全マップは、参加者の走行データから急ブレーキ、急加速、急ハンドル、スマートフォン使用、速度超過などの危険運転挙動の発生場所を可視化したものです。1か月で収集された総走行距離は約55万3,000キロメートルに達し、これは地球13周分(1周約4万キロメートル)、大分県内の全道路の総延長(約18,500キロメートル)の30倍にあたる膨大なデータとなりました。
このデータには、高速道路や主要な幹線道路だけでなく、生活圏の道路や抜け道も含めた、県民が日常的に利用する道路の詳細な情報が含まれています。この膨大なデータが、たとえば速度制限を新たに設けることにより通学路を安全にする、標識を新設するなどの対策に活用されることで、より効果的な事故防止策の立案が期待されます。
収集データから見えた特徴
- 急加速…大分駅周辺を中心とした幹線道路で発生頻度が高い
- 急ブレーキ…飛び出しなど交通事故リスクが高い地点を特定。裏道の生活道路にも危険が潜む
- 急ハンドル…大分駅前のロータリー周辺でUターンに関連した急ハンドルが多発
- スマートフォン使用…時速5キロ以上で走行中に画面が動作している状態を検知する仕掛けで、多くのスマホ使用が記録された
- 速度超過の分析…幹線道路での速度超過が目立つ一方で、制限速度の見直しが検討されるべき道路の存在も示唆
立命館アジア太平洋大学との連携でボーダーレスな交通安全の実現へ
続いて、あいおいニッセイ同和損保と立命館アジア太平洋大学(APU)との連携についても紹介されました。APUでは、110ヶ国から約3,000人の留学生が学んでいます。異なる交通文化や交通ルールの中で育った学生たちにとって、日本の交通ルールの理解は容易ではありません。
たとえば、逆三角形の道路標識について、日本では「徐行」と「一時停止」で区別されますが、海外では基本的に「徐行」のみを意味するケースが多いなど、文化的な違いが安全運転の障害となる場合があります。このため、あいおいニッセイ同和損保とAPUは協力して、AI技術を活用し英語の交通安全教育動画の制作に取り組みました。これにより、基本的な交通ルール、日本の運転免許制度、自賠責保険を含めた被害者救済制度などを、外国籍の学生の皆さまにも正確に理解してもらうことを目指しています。
県内全域では約2万人の在留外国人が生活しており、今後は多言語の交通安全教育教材を作成し、学生だけでなく、外国人労働者や訪日観光客の交通安全向上にも貢献していく計画です。

立命館アジア太平洋大学(APU)事務局次長 栗山 俊之 氏
プレゼンテーションに立った、立命館アジア太平洋大学 事務局次長・栗山俊之氏は「多くの学生たちが、日本という新しい環境で成長し、安全な生活を支援することが私たちの使命です。交通安全は単なるルールの問題ではなく、異文化理解の一環であると捉えています。母国とは異なる交通文化の意味を理解することで、学生たちは異国の社会をより深く知り、そのことが真のグローバル人材として活躍する姿につながっていくものと考えています。」と報告しました。
参加者および後援団体などから寄せられた声
「SAFE TOWN DRIVE OITA」は、交通安全に関連するさまざまな団体の皆様に後援していただいています。表彰式典の後、後援団体の皆さんは次のように語られました。
後援:大分県 生活環境企画課
大分県生活環境企画課で交通安全推進班主査の野田豊氏は、「運転手それぞれが客観的に自身の運転技術を確認できるシステム、そしてエコドライブにチャレンジするという取り組みが、交通安全の推進に寄与するという点から、大分県としてSAFE TOWN DRIVE OITAを後援させていただくことになりました」と、県としての関わりの経緯を話してくれました。
上位入賞者のハイスコアについて聞かれると「急ブレーキ、急ハンドル、速度超過などを意識して運転することは、当然交通事故防止につながると思います。コンテストが終了しても引き続き、参加された皆様やこの取り組みを聞いた方々が日常から安全運転を徹底していただくことを期待しています。そのことの積み重ねが1件、また1件と交通事故の減少につながっていくと考えています」と、日頃から安全運転を意識してほしいと呼びかけていました。
後援:公益財団法人 大分県交通安全協会
広報誌の発行やポスター・看板の掲示など、さまざまな交通安全の啓発活動を実施している大分県交通安全協会の井上俊郎企画指導室長は、自身もチームの一員としてコンテストにエントリーした結果について「全項目に気をつけていくのは難しく、元警察官という立場上、プレッシャーも感じながら日々の運転に取り組みました」とコメント。
「年齢を重ねてスピードは出さなくなりましたが、気をつけても急ブレーキと判定されてしまい、昔からの癖に気づかされました。チームで競ったことで、足を引っ張るわけにはいかないという思いから、より一層交通安全を意識した運転ができるようになりました。こうした取り組みが広がれば、交通事故減少につながるのではないかと思います」と、安全運転に対して日常から継続的な意識を持つことの重要性を指摘していました。

公益財団法人 大分県交通安全協会 総務部企画指導室長 井上 俊郎 氏
後援:大分県損害保険代理業協会
県内にある損保代理店110社が加盟する大分県損害保険代理業協会の竹内繁会長
「直接的に交通安全への理解を深め、促進できる機会を作っていただいたことを感謝しています。当協会としても、ぜひ参加し、応援したいと考えました。私たちは仕事上、事故が起きてしまったあと、ドライバーの方たちと対話をする機会が多くなっています。この時、個人の主観ではなく、運転の様子を客観的に振り返ることのできるシステムは、非常に心強い存在です。データに基づいて、一人ひとりが運転の癖を知り、改善していくお手伝いをできればよいと思います。」

一般社団法人 大分県損害保険代理業協会 会長 竹内 繁 氏
「SAFE TOWN DRIVE OITA」今後の展望
交通安全の重要性は誰もが認識していますが、実際に事故ゼロの社会を実現することは決して簡単なことではありません。今回は安全運転スコアの可視化、科学的データの提供によって、楽しみながら安全運転を身につけ、さらにその成果を地域全体の課題解決に活用するアプローチを示すことができました。これらを単発のイベントで終わることなく、持続的な展開を通じて、より多くのドライバーの意識改革を促していくことが今後の大きな課題となります。
安全運転の徹底は、事故そのものの減少につながることはもちろん、エコドライブによるCO2排出量の抑制、事故が減ることにより車両損傷が少なくなった結果の産業廃棄物削減といった副次的効果も期待されます。損害保険会社としては、事故発生時に頼りになるという従来の役割に加え、テレマティクス技術によって事前のヒヤリハット情報を地域に還元し、事故を未然に防ぐ動きも加速させたいと考えています。
収集された膨大な走行データは、交通安全以外の分野での活用も期待されています。たとえば観光振興では、走行ルートの分析により効果的な観光プロモーションの素材として活用できる可能性があります。また、走行中の振動データを分析することで道路修繕箇所の特定に役立てたり、安全運転の徹底によるエコドライブでCO2排出削減効果を数値化したりと、多方面への応用が検討・実施されています。
高齢社会においては、元気な高齢者が安心して運転を続けられる環境づくりも重要なテーマです。客観的なデータに基づく運転技術の評価により、自信を持って運転を継続できる高齢者の増加は、地域の活性化にもつながるでしょう。
主催者であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社大分支店で、本イベントの企画立案から実行までを推進した大分営業開発課・藤田京佑さんは、初回にもかかわらず多くの団体や企業が理念に共鳴して参加してくれたことには「想定以上でした」と述べ、「今後は、参画いただいている様々な企業・団体様同士をつなげていく「アレンジャー」としての役割発揮をすることが今後の私たちの使命だと考えています。弊社だけが中心にいるのではなく、「SAFE TOWN DRIVE OITA」の仲間同士が大分県のために役立つような枠組みを作れるようにリードしたいと考えていますし、この取り組みがその第一歩になれば嬉しいです」と今回の成果を足がかりに、さらに大きな社会的インパクトを生み出していきたいと決意を語っています。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 大分支店 大分営業開発課課長補佐
藤田 京佑 氏
今回のコンテストは、SAFE TOWN DRIVE OITAの取り組みに賛同する企業や自治体などのメンバー、約200チームで実施されましたが、将来的には一般市民への参加拡大も視野に入れています。今後も、「語り広げる、仲間を増やす」という理念のもと、セーフタウンドライブコンテストの取り組みを通じて、地域全体を巻き込んだ交通安全文化の醸成と地域社会の発展に継続的に貢献していきたいと考えています。
参加者一人ひとりの意識変化から始まった小さな取り組みが、やがて大分県全体の安心・安全な交通環境の実現につながっていくことを期待しています。
あいおいニッセイ同和損保では、このような取り組みを全国各地で実施しています。今後も様々なイベントを通じて、交通安全・CO2削減に取り組み、よりよいまちづくりを目指した活動を行っていきます。
「セーフタウンドライブコンテスト」は、全国各地で随時開催されています。
▼詳しくはこちら



.png)